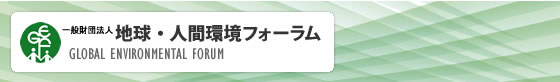持続可能な原材料調達
「パーム(椰子)油とCSR」開催報告
「ボルネオ島サバ州でのオラウータン保護活動」(4)
イサベル・ラックマン-アンクレナズ(Dr. Isabelle Lackman-Ancrenaz)/NPO「Hutan(ウータン)」代表
●キナバタンガンでの様々な取り組み②
学校での自然教育プログラムは非常に重要です。今や自然保護は緊急の課題で、何十年も待つことはできません。そのため、子供たちにいかに環境や自然保護が大事かということを教えます。学校や研究所、そして森の中でも教育を行うことで、自然の大切さを実感してもらいます。また、能力形成も重要です。スタッフには14,15歳までしか学校に行かなかった人もいるので、トレーニングは非常に重要です。私は、博士号を取得していますが、役に立たないこともよくあり、今必要な事は、働きながら学んでいます。現在、スタッフの多くが非常にすばらしい資格を持っています。植物に関しては私よりずっと知識を持っている人もいます。寄生虫やホルモンに関する知識を蓄えた人もいます。外部の研究者が技術を教えてくれます。保全活動能力の向上のために、政府の役人のためのトレーニングも行っています。
先ほども言いましたが、マレーシアでは開発の代わりとなる観光も非常に重要です。地元に、利益を与えることなく森林保全をすすめることは不可能です。資源の必要な村人は、森林管理者と対立してしまいます。森林保全や保護区の存在意義を理解してもらえるような解決策が必要です。オランウータンや象から利益を得る方法は、観光です。キナバタンガンではホームステイプログラムを実施しています。村の一般家庭に滞在して、伝統的な暮らしをします。おいしい食事出て、村人は非常に暖かく迎えてくれます。簡素ですが、訪れた人たちは、皆すごく喜んで帰っていきます。村人のうち8人は、観光客が野生のオランウータンを見ることのできるツアーを組み、会社を始めました。
少し古いですが、2003年から2004年の利益共有プロセスの数字では、
ツアー会社の株主のみならず、村の人たち-ボートを操縦する人、バスの運転手、お店の人、ガイドの人、地元の文化関係の人たち、ホームステイの人たち-すべてにとってメリットになります。利益共有プロセスの中で、村の外に出たお金は3%に過ぎません。その残りすべてが利益共有プロセスの中に入っています。このモデルは上手く稼動しており、他の地域でも取り入れていければと思っています。
漁業者と一緒にやっているプロジェクトもあります。キナバタンガン川にはものすごく大きくて美しいエビが住んでいます。ここには5,000もの網、罠がしかけられています。
エビの罠は、三ヶ月に一回作り直さなくてはなりません。漁業者は親戚一同、木の皮をはいで網を作っており、森林管理者と争いになります。今まで何代にもわたってやってきたことを、なぜ今やめなければならないのか、これからどうやって家族を養っていけばいいのか、と言われてしまいます。ですから、哲学的な、非常に難しいディスカッションを何年間も続けました。議論に耐えられなくなった村人の一人が、罠に別のものを使用することを提案しました。私たちは隣町の金物屋で、プラスチックのワイヤーメッシュを購入しました。現在はエノリウムやプラスチックといった、建築廃材を利用してワイヤーメッシュの網を作っています。このアイディアうまくいきました。5年経ちましたが耐久性もあり、今では村の漁業者は皆、メッシュの罠を使っています。これは森林保全とオランウータンのために大いに役立ちました。
苗木を育てることも、分断されている緑の回廊も再構築しなくてはなりません。政府や大きな組織が川沿いや、伐採された地域に植林してくれることを願っています。村人は、苗木畑があれば、大きなコンサベーションNGOや政府に販売できると考えています。すでに苗木を育て、コンサベーションNGOが買い取った例もあり、地元にとって代替収入源のひとつになります。
●更なる改善に向けて
解決策はあります。しかし、まだ民間企業や政府との協力がかなり必要になります。そしてより多くの解決策を考える必要があります。RSPOとパーム油業界が、環境影響の少ない業務方法を考え、認証を導入しようとしていますが、これはすばらしいことだと思います。キナバタンガンでは解決すべき問題が多々あります。法律には、オランウータン、象やその他野生動物が分断化した森からもう一方の森に移動できるように川沿いに木を植えるよう明記しています。プランテーションそのもの問題なのではなく、それぞれの森に連続性がないことが問題なのです。RSPOの行っていることはオランウータンや象といった野生動物の保全にとって重要な役割を果たしています。ありがとうございました。
(2007年10月10日東京都内にて)
●戻る
<前ページへ>
-
●関連情報
- シンポジウム「生物多様性と企業の役割~パーム油の現場から~」(2009年2月)開催案内
- 「発展途上地域における原材料調達グリーン化支援事業 」の報告書はこちら
- 「持続可能な原材料調達 連続セミナー」はこちら
- 公開研究会「輸送用バイオ燃料利用の持続可能性と社会的責任―ブラジル報告を中心に」